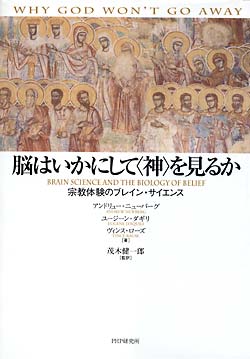|
04/7/7 脳 は い か に し て 〈神〉 を 見 る か 副題: 宗教体験のブレイン・サイエンス アンドリュー・ニューバーグ、ユージーン・ダキリ、ヴィンス・ローズ 著 PHP研究所 (2003年3月出版)
私たちが感じたり、考えたりすることは、すべて脳の働きであることは、今や常識である。生きているとはいえ、物質の塊である脳の中で、電気的・化学的反応が起きている。それが私たちの精神活動なのであって、それ以上の神秘的なものはない。一方、人は自分を越えた存在を感じ、霊的なものをイメージし、自分を一個の魂と自覚し、その魂が永遠に生きることを信じる。偉大なるものへの畏敬の念を共有することによって、宗教ができ、イメージや言葉をもって表象される人格神に帰依する。それは単なる知的理解を超えた宗教的経験をもたらす。 現在、脳を研究している大部分の科学者、そして彼らを含むもっと大きな自然科学者集団の多くは、脳の物質的解明が進めば、宗教的経験は、脳のある特別な活動状態として説明されてしまい、それ以上の何の神秘も残らないだろう、と信じている。以前読んでここで紹介したフランシス・クリックは、その著『DNAに魂はあるか』で
という仮説を証明するのが脳科学だとして、そのための道筋をつけようとした。 一方、宗教を信じる人、特に瞑想などの宗教的経験を究めた宗教者たちは、彼らの体験を、これほどリアルなものはないと主張する。世界中で今生きている人々の何割かは、ゴッドとアッラーとかの名で呼ぶ超越存在をホンモノとして、真剣にあがめている。それは無知ゆえの幻想に過ぎず、脳についての知識が進むにつれて、やがて消え去っていくことになる迷信なのだろうか。 著者たちがこの本で書いているのは、宗教者の宗教的経験には脳活動の裏付けがあること、宗教的感性は進化の過程で人類の誕生とともに誕生した本来的なものであること、特定の脳活動を成り立たせる超越的なリアリティの存在を否定できないことなどで、宗教を脳の神経活動と結びつけて積極的に評価しようとしている。英語の原題は、「神はなぜ消え失せないのか」 であるが、科学が進歩しても、人間にとって神がなくならないのは、脳がそのようにできているからだと、科学者の立場から主張している。 著者たちは脳の活動状態を画像としてとらえる高度な実験装置を駆使している。 SPECT(単光子放出断層撮影法)と呼ばれる装置である。CTスキャンや脳ドックで使うMRI装置と同類のものと思えばよい。脳の中での血液の流れの大小をCTスキャンと同じような断層写真で撮ることができる。チベット仏教の瞑想のできる人を被検者とする。暗い実験室で瞑想してもらい、その瞑想が極致に達したときに、合図をもらい、直ちに造影剤(この場合は放射性物質)を注射し、脳の血流を装置で調べる。宗教的な神秘経験をしているときに脳のどの部分が活性化したり、不活性になったりするかを調べるのである。最先端科学が宗教現象を解明するのに使われる。 その結果、彼らは宗教的神秘経験と密接に関係する場所を見つけた。それは専門用語では「上頭頂葉後部」と呼ばれているが、この本では「方向定位連合野」と、その機能が分かりやすい名前をつけている。私たちが、自分のまわりの空間の中で、何処に、どのような向きなり傾きでいるかなどを、意識にとどめている部位である。深い瞑想に入ると、この部分の活動レベルが極端に低下することが分かった。方向定位連合野に流れ込んでくる感覚器官からの信号が遮断されるらしい。 宗教的神秘体験では、瞑想者は、自分と外界との区別がなくなり、自分が孤立した存在ではなく、万物と分かちがたく結ばれている、という実感を味わうらしい。そのことと、方向定位連合野の活動が低下していることとが密接に関係している。自分とまわりとの関係が溶けて不分明になるらしい。これが著者らの発見である。そこのことから、著者らは、
などと主張している。 さて、これから先は二つの道に分かれる。ヒトの宗教体験に神経学的な根拠が得られたとして、考えようは二通りある。宗教的神秘経験は、儀式・修行などのくり返しによって、脳のある部位が、たまたま特殊な神経状態になったに過ぎないのであって、いわば幻覚なのである、と考えかた。 他方、ヒトの脳に神を感受する部位があることが分かったとはすばらしい。いわば、それが神を見る眼、神の声を聞く耳、究極的なものを垣間見る窓なのであって、超越存在としての神は、ヒトの持つその神経機能を通して顕現するのだ。その機能を研ぎ澄ませることが、神と出会う道なのである、とする考え方もありうる。 この二つの考え方のどちらを取るか、それは科学を超えた判断である。リアルなものはすべて物質世界の中にあり、物質世界以外にリアルなものはない、との自然主義の立場(それが自然科学の立場であるが)に立って進めてきた研究が、究極的なものを見る窓を発見したことで、著者らは、物質的なものを越えたリアリティーの方向を示唆しているようだ。 ただ、著者らは、神秘主義に傾いており、ユダヤ・キリスト教、あるいはイスラム教のような、人格神をあがめる宗教は、究極的な一者の不完全な描像に過ぎないと、諸宗教が「一なるものへ」と解消することが正しいとしている。 日本でいま脳科学の最前線をになっている一人である茂木健一郎が、この翻訳を監訳し、あとがきを書いているが、彼は、宗教的体験がヒトの脳の働きによるという神秘以上に、脳の神経活動によって主観的体験、すなわち意識なるものが立ち現れてくること自体が、現在までの脳科学で解明できない神秘そのものなのだとしている。 脳の働きを窮め尽くせば、意識も宗教心もすべて分かってしまって、それ以外のなんの神秘も残らないとする楽観的自然主義と、どんなに究めても、意識には窮め尽くされないものが残る、それはヒトの生まれつきの認知能力に限界があるからだ、とする悲観的2元論とが、脳と心の問題をめぐって並立しているようだ。脳の科学と哲学の学びは、まだまだ果てしなく続きそうである。 |