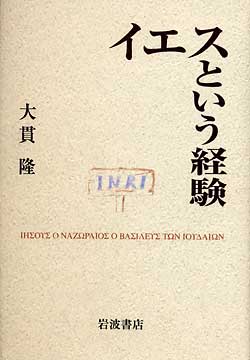|
04/4/27 イ エ ス と い う 体 験 大 貫 隆 著 岩波書店(2003年10月出版)
イエスは、神の子であったか。 キリスト者でも何でもないものにとっては、どうでもいい質問だろう。しかし著者は、この問題に答を見つけることが、ブッシュのアメリカの迷妄を正すことになる、との思いで、この本を書いた。そのように「はじめに、本書の課題と方法」にも、「あとがき」にも書いてある。 書かれていることは、上の問いに対する、新約聖書の文献学的な研究にもとづく答である。そのことと、ブッシュのアメリカがイラクでやっている間違った戦争との間には、とてつもない距離がある。しかし著者は、この疑問にきちんとけじめをつけ、そこからアメリカのキリスト教原理主義を批判していかなければ、今後も同じような間違いをアメリカが犯し、世界中をますます混乱させるに違いない、との信念にもとづいて、これを書こうとしたようだ。その情熱のゆえか、わずか1ヶ月でこの2百数十ページの本を書き上げたという。書かれてあることは、決して筆が走っておらず、冷静で説得力のあるイエス論である。 私はこれまで数多くのイエス論を読んできたが、大部分はキリスト教の立場を最終的に守ってしまうか、あるいは偏ったイエス像(たとえば過激派イエスというような)を読み込ませすぎたかであった。この書物は、最新の学問的成果に基づき、これまでになく納得できるイエス像を提示していると思う。 イエスの言行を伝えるのは、新約聖書冒頭の4つの福音書である。これらはイエスの死後数十年以上経ってから、伝承にもとづいて編集されたものである。生前のイエスが語った言葉は、伝承の過程で、正確に伝わったわけではない。イエスの死後、弟子たちは、イエスの生涯とその死がどのような意味を持つかについての共通理解を作り上げていった。大貫は、それを原始キリスト教会の「標準文法」と呼んでいる。この標準文法に沿って、生前のイエスが語った言葉に粉飾が加えられた。粉飾という言葉が失礼なら、善意の言い換えや加筆がなされた。それが今私たちが手にする4つの福音書である。 福音書の成立の歴史を分析し、各文書を文献学的に詳しく調べることで、生前のイエスが語った「なまの言葉」と、その後の変更・加筆部分とを、より分けることができるだろうか。古くは19世紀から始まって、20世紀いっぱい、沢山の研究が積み重ねられてきた。ある時期の典型的結論は、「不可能!」ということだった。福音書に記されているイエスの言葉も行動の記録も、原始キリスト教会が堅く信奉した「標準文法」にあまりにも色濃く染まっていて、生前のイエスの言葉を抜き出すなどとうていできない。むしろ「標準文法」こそが福音書の純正な部分であって、生前のイエスの言葉を求めるなどどうでもいいことだ、とまでされた。 「標準文法」とは、キリスト教の正統的な教義である。イエスは単なる歴史的人物であるだけではない。天地創造以前から神の独り子として存在し、この世を救うために、地上に遣わされ、神の言葉を伝えた。生涯の最後、十字架上の死は、人間の罪をすべて背負っての贖罪の死であった。そのイエスが救い主キリストであることを信じることによって、人は救われる。キリストはその死を越えて復活し、今は神のもとにある。やがて再びこの世にやってきて、信じるものと不信のものとを裁き、信じるものは天国に受けいれられる。これが「標準文法」のあらすじである。 カトリックからアメリカ原理主義キリスト教まで、この「標準文法」は、共通して信奉されているが、その受け止め方には、さまざまなニュアンスがある。十字架上の死による赦しを、日々の生活のなかで実体的に受け止めるカトリック、信じることによって救われることを強調するともに、「標準文法」の古代的表現を現代的な解釈で補っていこうとする主流派プロテスタント教会。すべてを言葉通りに受け止めて解釈を許さず、特にキリストの再臨による裁きを強調し、非キリスト教徒を地獄に堕ちるものとして差別視する原理主義者たち。そんな色分けになるだろうか。 さて、先ほど書いたように、聖書の文献学の一時期の結論は、生前のイエスの言葉を抜き出すことはほとんど不可能ということだった。しかし、その後、新約聖書文献学の潮流は変わってきたようである。イエスの時代の社会的状況についての知見が進んだこと、また文献学の手法に新たな進歩があったことなどから、必ずしも不可能ではなく、これこそイエスの語った言葉だといえるものを、標準文法に染まった記事の中から汲み上げることができる、という肯定的な方向へ変わってきた。 大貫は、そのような最近の新約聖書学の成果をもとに、あらためてイエス像を描き直そうとする。それにより、キリスト教原理主義者の信奉するキリスト教が、イエスの原像からいかにずれているかを明らかにしようとする。 著者大貫の方法はこうである。福音書の個々の記事を分析する。その際、言葉あるいは文脈に 「標準文法」、すなわちイエスを神の子キリストとする考え方に染まった部分があれば、その部分は、伝承の過程で変更・加筆されたものとし、その色彩のない部分こそが、生前のイエスの言葉であろう、とするのである。福音書には相互に重複している記事が数多くあるので、それを比較対照することで、どのような加筆がなされたかも分かる。 丹念な文献学的な研究の結果は、その一部が本書に例示されているにすぎないが、本書で大貫の意図するものは、読み直しの詳細をあげることではない。むしろ、個々の記事を繋ぐことで見えてきたイエスの原像の提示である。イエスを突き動かしていた根源的なものごとが何であるか。イエスの言行の原動力となっていた、イエスの抱いたイメージの総体は何か。大貫はそれをイエスのイメージ・ネットワークと称する。 大貫は、これまでのキリスト教の伝統的解釈に反して、イエスは神の子ではなかったし、自分もそのように自覚していなかった。むしろ普通の人だったし、そのように自認していた、とする。イエスが特異だったのは、それまでの戒律にしばられたユダヤ教のあり方を批判し、決別したこと。さらには自分の師であった洗礼者ヨハネの唱えた神の裁きが近いとのきびしいメッセージともたもとを分かったこと。イエスはまったく新しい地平に立ったのですある。それは、きわめて肯定的な意味での「神の国」がすぐ来ること。いや、もう天上ではそれは始まっていること。そのことを力強い言葉で語り、またそれを身をもって示そうとしたのが、イエスだった。 イエスのイメージ・ネットワークを、大貫は 「宇宙の晴れ上がり」 という言葉で表現する。なんでも最近の宇宙物理学がビッグバンについて言っている言葉を借りているらしい。それはたとえばイエスの語ったとされる、有名な 「山上の垂訓」 の一部に現れてる世界のイメージである。
ここでは、善と悪とか、価値と無価値というような一切の区別が取り去られて、すべてが神の無条件のはぐくみ、無条件の肯定のもとに置かれている、と大貫は言い、それを 「宇宙の晴れ上がり」 という言葉で代表させる。この肯定的世界が神の国であり、それがすでに始まっている、とイエスはのべ伝えたかったのだ、と大貫は解釈する。その文脈で、福音書全体は意味のネットワークとして読み直される。ここでは、その紹介をすることは、やめておこう。当時の社会で差別されていた人々に、イエスは、神の国はあなたがたのものであると語ったこと、イエスの行った数々の奇跡、イエス独特のたとえ話などが、上記のイメージネットワークの視点から、解き明かされる。 それでは、イエスの最後の死は何だったのか。「標準文法」は、イエスにとって、死ぬことそれ自体が使命だったとする。キリスト教批判の人たちは、イエスはユダヤ教に対する反逆者として殺されたのだとする。大貫はまったく違う解釈だ。最後の最後までイエスは、神の国の現実的な到来を信じながら、それが果たされないまま、自分が殺されてしまうことを理解できずに、絶望の死を遂げたと考える。歴史上の人物イエスにとって、それが終わりであった。 イエスの死後、弟子たちが、イエスの死の意味をとらえ直すことで、キリスト教は出発した。それはイエスのイメージネットワークを組み替え、イエスを神の子とし、イエスの死に意味をつけることで出来上がったものである。そこまで大貫は断定していないが、はっきり言えば、その後のキリスト教とイエスとは別のものだ、ということである。 本書の最後の部分で、古代の神話的世界観のなかで生きたイエスが、当時の言葉で語ったイメージネットワークを、現代のわれわれの言葉でとらえ直す試みを、大貫は提示している。私にはよく理解できなかったし、本書の重要な部分ではない。 イラクでの戦争、アルカイダの全世界規模のテロリズム、イスラエル対パレスチナのいつ果てるともしれない抗争、ロシア国内でのチェチェンの抵抗。現在の世界情勢をながめてみると、戦争やテロリズムが、依然として、あるいは前の時代にも増して、宗教の問題と結びついていることに気づく。「依然として」としてと書いたのは、世界史上の数々の戦争は、宗教の対立が原因となっていたことを、私たちは知っているからである。「前の時代にも増して」と書いたのは、宗教が表だった要因と必ずしもいえなかった帝国主義戦争、ファッシズム対民主主義の戦争、そして冷戦という時代が終わった現在、中東におけるさまざまな戦乱の原因にイスラム対他宗教という対立があること、その戦乱に最強の「帝国」として手を出しているアメリカ合衆国そのものが、宗教色の濃い国であることを念頭に置いてのことである。 人々に安らぎと癒しをもたらすはずの宗教が、どうしてこのようにひどい抗争と殺し合いを引き起こしてしまうのか。それぞれの宗教の中に、あるいは宗教ということ自体の中に、何か根源的な問題があるに違いない。私たちは、宗教を乗り越える、あるいは脱することでしか、この世界状況を解決できないのだろうか。しかし宗教は、人間が生きていくために不可欠のものなのかもしれない。人間であるということと、宗教を信じることとは、深いところで結びついているのかもしれない。進化の過程で生まれた人類(ホモサピエンス)の脳の構造の中に、宗教を生み出す構造と機能がビルトインされているのだろうか。 宗教は絶対者を立てる(仏教は違うのかもしれないが)。絶対者は絶対であるゆえに、他の絶対者を認めない。宗教は互いに相容れない。あの神様も、この神様も、それぞれにいい、などと互いを相対化のレベルに置いては、信じるという行為が成り立たない。 すべての宗教は、それぞれの歴史を持っている。ある歴史的経緯のなかで、特定の時代に、特定の民族、特定の地域で発生し、特異な形に発展し、伝承され続けてきた。もし「人類みな兄弟」という普遍的な考え方に立つことができれば、それぞれの宗教を、ある歴史上の現象として、相対化できるのではないか。個々の宗教の出発点をよく確かめ、特に教祖の根源的な主張が、どのような点にあったかを、特殊化をできるだけ避けて(特定宗教の言葉を使わずに)、普遍的な人間存在という観点から見直すことで、共通基盤のもとに置き直すことができないものか。 教祖の根源志向は、人間存在に対する普遍性のある洞察から発していたものが、宗教という制度になっていくなかで、教条化され、形式化され、排他的に変わっていったのではないか。そのことを、調べ直すなかで、根源的・普遍的なことではなく、特殊で些末な部分こそが、形式化されて墨守されてきたことが分かってこないか。その部分は、根源的なことに比べれば、二次的なこととしてこだわらなくてもいいのだ、という寛容と知恵がでてこないか。根源的なこと自体も、古い始祖の時代の言葉ではなく、現代の言葉で理解し直してみれば、共通理解の糸口が見いだせるのではないか。こんな方向でしか、宗教間の対立は乗り越えられそうにない、と思う。だが、それは、とても難しいことだ。そんな方向には行かず、人間と社会は愚かであり続けるに違いないという悲観論も、すぐ背中合わせにあるのは承知だ。 以上は私の感想の付け足しだが、大貫が再発見したイエスは、そのような形式宗教の枠や諸宗教の対立を越えた人だった。そのイエスから、キリスト教なるものが生まれてきたのは、大きな歴史の皮肉であろうか。まして今イラクに手を出し、イスラム教徒とはげしく対立しているアメリカの、精神的基盤であるという原理主義キリスト教が、このイエスをかついでいるなんて、なんということか。ブルース・バウアーの書いた「Stealing Jesus」 のタイトルを借りれば、「おまえら原理主義者よ、イエスを盗まないでくれ!イエスの本当の姿をもっとよく知ってくれ!」 というのが、紹介した書物を書いた、大貫のいいたかったことだろう。 |