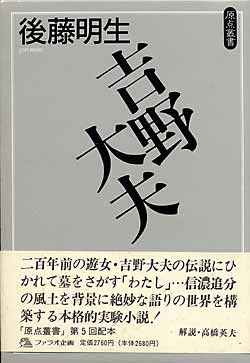|
02/9/1 吉 野 大 夫 後 藤 明 生 著 ファラオ原点叢書(1991)
新刊ではない。上記のように、1981年に出版され、その年に谷崎潤一郎文学賞を得た作品である。それをなぜ今頃読むか。それは信濃追分への興味、さらには「場所の物語」への趣向ゆえである。 信濃追分は、今は軽井沢町の一部となっているが、古くから高級な別荘地として名高い旧軽井沢や、西武系会社の開発で大衆化した中軽井沢(かつては沓掛と呼ばれた)と違って、浅間山麓の寒村である。堀辰雄らがこの地に住んで以来、文人や学者が好んで山荘をおくようになった。 ワイフの母校がここに山荘を持っていて、卒業生が使えたのと、ワイフの親友夫婦の山荘があり、泊まり込みで話し合うのを楽しんだりしてきたことで、ずっと以前、多分30数年以上前から、この地を訪れるリピーターになっていた。なだらかに傾斜した火山性の土地に、根を深く張れないながらも、唐松やアカシアなどの雑木の林が広がっている。その林の中にぽつりぽつりと、山荘が点在する。豪華な別荘ではない。つましいものが多い。細い道がそれらの間をつないでいる。歩いていてあまり人に出会うこともない。ときおり林が切れて視界が開け、雄大な浅間が目前に姿を見せる。そんな人里離れた風情の追分がとても気に入っていた。 とはいっても、そこを訪れ、自然を愛で、友人たちと交流するのを楽しんではきたが、場所としての追分に格別の興味を持たなかった。忙しい日常からの逃避が精一杯であり、それ以上の好奇心を拡げるゆとりなどなかったからだ。 しかし、この土地への興味は潜在していたのだろう。この夏の滞在を前にして、にわかに、この地についての関心が高まった。もともと、住む場所、訪れる場所について、その土地の歴史や風土(先に書いた「場所の物語」)に人一倍興味を持つたちである。関心を持つと凝り、深入りする。芋蔓をたぐるように、追分に関する本を、つぎつぎに、あれこれと読んだ。堀辰雄と立原道造などからたぐり、中村真一郎の「火の山の物語」(筑摩書房、1988年)、そして近藤富枝の「信濃文学譜」(中央公論社、1990年)などを経て、この本にたどりついた。今では、これまで読んだことのなかった後藤明生(めいせい)にどっぷり浸かっている。 そんな中でも、この「吉野大夫」は、宝石を掘り当てたような手応えを感じた。私が追分に興味を持って調べるとしたら、こんな風にしたいだろうな、という、まさにその通りのことを作者が実行し、それを小説にしているのだ。何か自分の性向・考え方・表現にぴったりの作者に出会った、という感じである。何かの名作を読むとき、これぞ自分の読みたかったこと、自分の書きたかったことを、そのものズバリで表現してくれている、そういう気がすることがあるものだが、この書物が、私にとってのそれであった。
追分は、江戸時代には、江戸から碓氷峠を経て、この地に至った中山道が、諏訪方面へ向かう本道と、長野善光寺方面へ向かう北国街道とが分岐する場所の宿場町として栄えた。交通量の多い国道18号線から切り離される形で、今でも追分旧街道と、分岐点の通称「分か去れ」に、往時の面影が若干残っている。参勤交代の宿所本陣として、また一般人の旅の宿として、江戸時代には賑わった。宿屋が四十数軒、のきを連ね、百人から二百数十人の飯盛女がいた。飯盛女とは非公式の遊女である。 貧農の娘が買われ、遊女に身を落とし、年季が明けないうちに病んで死ねば捨てられる。そういう悲しい物語が残っている。その中に「吉野大夫」という、飯盛女らしからぬ名前を付けられた遊女がいたらしい。しかもこの女は、どういう罪を着せられたのか、斬罪になって最期を遂げた。そんな伝説が、この里に伝えられている。 この作品は、追分に在住する小説家が、この吉野大夫伝説を調べていく次第を、そのまま小説にするという構成を取っている。ちょっとややこしい。吉野太夫のことを調べ、その生涯のこと、特にその劇的な最後のことなど、書くに値することが分かったうえで、吉野大夫を主人公とした物語を小説にするのが普通だろう。 ところが、この作品では、吉野大夫のことに、たまたま興味を抱いた小説家が、あれこれ調べていく,その過程そのものが小説となっている。一章ごとに雑誌に連載したらしい。だから始めるときには、終わりがどうなるかなど見当もつかないままに書き始めた様子である。こんな具合である。
この、ちょっと人を食ったところがいい。真面目さゆえのユーモアとでもいうものが、全編を貫いている。5,6年も前から興味を持ったという。その間、調べが進行し、成果があったわけではない。とにかく、書くことにして、書き始めるのである。書き出しても、精力的に調べるわけではない。関心を抱きながらもあれこれと雑事に追われる山荘生活の日常を、主題とは関係なく描写していく。
追分には2種類の人が住んでいる。夏だけ山荘にやってくる、よそ者(最近では、四季を通じて住む人もいる。私らの親友夫婦もそうである)。その中でも小説家が付き合うのは、同業者や大学教授など、いわゆる追分文化人たちである。もう片方は、地元の人々である。彼らは、江戸以来の蔦屋だの、清水屋だのの屋号でたがいに呼びあっている。その両方の人々が、関わってくる。文化人たちと会ったおりに、吉野大夫のことを、さりげなく話題にしてみる。また別の折には、何とか屋の古老にも訊ねてみる。そんな行きつ戻りつの「吉野大夫調べ」の次第が、淡々と、詳細に、書いてあるのである。 吉野大夫の墓探しは、書き始めより2,3年前に成功していた。地元の人は知っていたらしい。しかしそれを世に知らしめたのは、この作品の産物の一つかもしれない。今では軽井沢町の道しるべが立っているという。訪ねる人もあるらしい。墓碑には「春貞善定尼、享保廿卯天三月十八日没」とあるという。1735年、享保は将軍吉宗の時代である。元禄の爛熟のあとの改革の時期である。遊女町の粛正が行われ、一番目につく遊女が犠牲になったという説もある。 時間は経っていくが。吉野大夫調べは、はかどらない。おまけに途中で、この小説家(作者自身だが)は、病気で入院ということになる。そんな次第まで、物語の中に取り込まれている。第四章は丸ごと、その病院から知人に当てた手紙の形をとっている。すでに雑誌に発表した部分についての読者の反応まで出てくる。小説が、小説それ自体のことをリアルタイムで取り込み、入れ子構造になっている。そこら辺がまことにおかしい。おかしいというのは変だ、というのでなくほほえましいのである。 吉野大夫その人のことは結局わずかしか分からない。たしかに実在し、墓も見つかり、過去帳も見つかった。しかし、吉野大夫という名で呼ばれたかどうか、どんな人だったのか、悲惨だったと伝えられるその最後はどうだったのか。何が原因でそうなったのか。肝心のことは分からなかったまま、作品は終わっている。 吉野大夫の秘密を探り当てるのだろうかと、最後まで興味を持って読んできた読者は、なーんだ。ということになる。だが実は、これは吉野大夫の物語ではなく、吉野大夫のことを調べる小説家の日常の物語なのである。 そう思って読むと実に面白い。ある場合には、村の古老に聞いてみる会話がそのまま記録されている。それがなかなか核心に至らず、ちぐはぐにずれているのが面白い。ある場合には、この山荘村に住む学者、文学者と地元の人のパーティーでの会話が、格別吉野大夫のこととは関係ないのだが、だらだらと書いてある。それが吉野大夫のことを調べつつある小説家の暮らしぶりとして、淡々と出てくる。 吉野大夫とは、もともと京都島原の最高位の遊女に贈られる名前である。西鶴の「好色一代男」にも登場する。作者は、追分の吉野大夫に興味を持って調べるのだが、島原の吉野大夫のことも気になる。それでいろいろと調べてみる。専門家の論文・著書を読み、新解釈を応援したりする。そんな次第も書いてある。 そして、最後は、何一つ調べ尽くせずに、物語は終わるのである。些末なことに興味を持ち、それを調べる過程を楽しむ作家の物語、と単純にとらえてもいい。私のようにそれに共感できるたちの人には、結構楽しめる。信州追分という場所に土地勘があり、興味があるなら、もっと楽しめる。 自分の住む地域の「場所の物語}に興味を持つことは、かなり一般的なことだろう。私は、そうである。そのことが、東京街歩き、それもHPをごらんのように、住んでいる四谷あたりに偏った興味の源泉になっている。別に郷土史研究をやろうというわけではない。ただ自分の現住の場所へのこだわりである。そういう興味のあり方の一つの例として、いや典型例として、この小説は同じ趣向を持つ人間の気持ちをそそるのである。 どうも後藤明生には、そういう趣向があるのではないか。信濃追分については、「笑坂」(筑摩書房、1981年)という短編連作小説を書いている。また首都圏での終の棲家となった、新興地幕張のマンションでも、近くにある小さな丘に興味を持ち、「首塚の上のアドバルーン」を書いている。関心の所在については、吉野大夫が首塚に置き換えられたものといえる。 だが作者には、もう少し高尚なねらいもあったようである。それは、地域地域にありがちのうわさ話が、どう形成され、広まり、伝わっていくか、という社会現象への省察である。何も実態のないことに尾ひれがついて、まことしやかに人々の口にのぼり、拡がり、定着するという人間社会のあり方の考察である。著者は、本の後記でこういっている。
まあしかし、これは脇のねらいであって、本筋ではあるまい。また、先の私のとらえ方は、自分の趣向に引きつけすぎであろう。多様な人間生活の一つの側面を、自分の日常生活の中でとらえ、それを文章表現として読者に問いかける、小説というものの本質面からこの作品を評価するべきなのだろう。そういう点では、劇的なストーリーをことさら避けて、淡々と筆をすすめる、この人の文学は、一つのスタイルなのだろうが、その辺への洞察力は、私にはない。だが、文章の快さだけはわかるのである。 後藤明生(めいせい)は、1932年生まれ。早稲田大学ロシア文学科出身。雑誌社に勤めながら小説を書き始め、36歳で独立。1971年から信濃追分で夏を過ごすようになる。「早稲田文学」編集委員。ゴーゴリ、ドストエフスキー、カフカなどの評論でも知られる。早稲田大学文芸部非常勤講師などを務めたあと、近畿大学文芸部教授、その後文芸部学部長となる。食道ガンを病み、1999年に67歳で亡くなる。現在入手可能なのは、いずれも講談社文芸文庫に収められている「首塚の上のアドバルーン」と「挟み撃ち」二冊と、「小説の快楽」(講談社、1998年)など、数少ない。忘れ去られつつある作家であろうか。「吉野大夫」は、本稿タイトルの下に書いた「名作再会シリーズ」と称する復刻版か、オンデマンドのCDで入手できる。各種文学全集に収められているものもある。「吉野大夫」は、小学館「昭和文学全集」などに入っている。 |