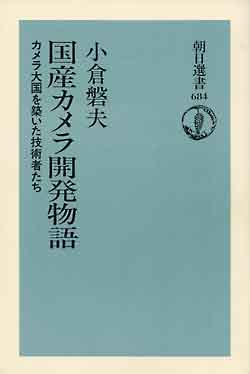|
01/11/11 国 産 カ メ ラ 開 発 物 語 小 倉 磐 夫 著
カメラというこの小さな機械は、ある種の男どもを、限りなく魅了する。写真を撮るための道具にすぎないのだが、撮ることより、そのための道具に凝る人がいる。写真趣味というより、カメラ好きである。田中長徳は、『カメラは病気』という本まで書いた。カメラ好きは、お互いに病気であることを認めあった上で、どちらのほうが病気が重いかを自慢しあう、変な習癖がある。この病気には、お金がかかるので、購買力に応じて、おのずと病気の進行には歯止めがかかるせいか、この病気で死んだ人はいない。かくいう私は、かつてはこの病気に対する耐性が強く、カメラ病患者を憐れみの目で見ていた方であるが、最近少しおかしくなり、多少病気に感染気味である。 さて、紹介するこの本は、この病気の本ではない。むしろ病原菌をせっせと作り出す技術者の苦労話である。今やこの病原菌を作り出す技術に関しては、日本は世界を独占している。ライカとかハッセルブラッドなど、特殊な菌を少量産み出している悪所がヨーロッパにあるが、これは、ごく特殊な感染体質を持った人間にしかうつらないので、あまり問題にならない。ただしライカ病は、一旦かかるとかなり悪質と聞く。 さて、冗談はさておいて、カメラに関して日本は、第2次世界大戦直後、ほとんどゼロの状態から出発した。それが今や全世界に、精密カメラとバカちょんカメラを独占的に供給するようになっている。ここに至るまで、カメラ・メーカーに働くエンジニアの間で、熾烈な技術開発競争があった。その歴史のエピソードを物語として書いたのが本書である。 カメラは、日本の得意とする生産技術開発が典型的に開花した世界である。独創的な原理・現象の発明がブレークスルーをもたらす、そのような種類の技術ではなく、既知の技術要素の組み合わせや改良が、システム化されることにより、諸外国が太刀打ちできないような競争力が生みだされる。そんな技術領域である。しかも、これまた日本独特であるが、技術力で他を圧倒するような1,2社が争うのではなく、ドングリの背比べ的に並んだ、数社の競争であった。どこの会社もそれほど特徴を出すことなく、似たような製品の開発を競い、ほんのちょっとの差で勝ったり負けたりしながら、圧倒的な勝ちも、全滅の負けもなく、それぞれのカメラは売れ続けた。これは驚くべきことである。 ニコン、キャノン、オリンパス、ミノルタ、アサヒペンタックス、コンタックス(かつてのヤシカ、現在の京セラ)、フジにコニカ、その他マミヤやゼンザブロニカ。ひとつの国のなかで、こんなに多くの企業が、それぞれ競争力を持ち続け、新製品を世の中に送りだし続けている。そしてそれ以外の国には、ほとんど何もない。そういう状態はどうして作り出されたのか。その不思議について、この本は、全体的な考察を与えない。しかし、ひとつひとつの技術開発の局面で、各企業のエンジニアたちが、いかに善戦したかについて、物語っている。 著者小倉磐夫は、カメラ業界の人ではない。一時期企業に勤めたことがあるが、そのあとは大学の先生である。そんな立場から、カメラ業界のエンジニアたちと会社の壁を越えてつき合い、各社の技術開発の裏の裏まで知りうる立場にあったようだ。 「アサヒカメラ」という写真雑誌がある。その種のものでは、日本で最も歴史が古く、権威のある雑誌だろう。この雑誌に「ニューフェース診断室」という連載欄がある。新しく世に出てきたカメラで、これはというものについて、写真工学的にさまざまな計測をおこない、一方では写真家が実写をするなどして、さまざまな方面から、客観的な評価を下す。これが同じスタイルで、もう45年も続いている。診断室だから、担当者はドクターとよばれ、数人が各種の評価項目を分担する。小倉さんは、この診断室を、最初はドクターの下請けとして、その後はドクターのひとりとして、ずっと関わってきた。 この診断室は結論が出ると、それをメーカーに見せ、反論があればそれを聞き、それも併せて掲載する。診断室の評価はおおむね辛い。だからメーカーには言い分が沢山ある。社長が怒鳴り込んできて、どうしても譲らなかったとか、いつまでも気まずいままになったこともあるらしい。そうこうしながら、カメラ・メーカーのエンジニアと40年以上も、つきあいを積み重ねてきた。その経験が本書のもとになっている。 アサヒカメラには、上記の「診断室」とは別のシリーズとして「Dr.オグラの写進化論」が10年あまり前に登場した。そこで、小倉さんは、エピソードの形で、カメラの技術開発に当たってきたエンジニアたちの苦労話を書いた。普通、企業の技術開発物語では、会社が表面に出て、技術者は名前が出ないものである。小倉さんの物語では、個々の技術者が名入りで登場し、顔が見える。そういうことで、会社という組織の中で、開発競争にしのぎを削らされる技術者たちの哀歓が、はじめて表に出される。
本書は、その「Dr.オグラの写進化論」シリーズの抜粋編である。同じものとして、すでに「戦争とカメラ」(1994年、朝日新聞社刊、2000年、朝日文庫)が出ている。本書はその続編である。両方とも読んでみたが、本書は前書の落ち穂拾いではない。まったく同格の、ひとつひとつが独立した話であり。同じように歴史をたどっている。どれを読んでも面白い。 一例を挙げよう。日本が世界の高級カメラの生産をほぼ独占することになったのは、一眼レフの製品化によるところが大きい。その草分けは、アサヒペンタックス(当時はアサヒレフレックスという上からのぞく方式)である。キーになったテクノロジーは、クイックリターンミラーだ。撮影の瞬間、ミラーが一瞬跳ね上がって、またピタリと元の位置に戻る。その原型のⅠ型が1952年に出たあと、2年後にクイックリタンミラー機構を備えたⅡ型が出た。当時のアサヒカメラの担当編集者は、ライカ型のボディーに、上からのぞくファインダーをつけただけの、こんなカメラが売れるかな、と疑問視したそうだ。それが日本のカメラを世界一にのし上げる技術の端緒だったのだから面白い。 この新方式のカメラをひっさげて、旭光学というベンチャー企業が登場したのである。社長松本三郎の先見性と情熱は大変なものだったらしい。焼け跡の町工場からスタートし、ろくな工作機械とてなかった。そんななかで、クイックリターンミラー機構を発明したのは吉田信行というエンジニア(後に専務)である。いよいよ製品化に着手するにあたって、資本金250万円の旭光学(社員100人足らず)が750万円の自動旋盤をフランスから買い入れたという。クイックリターンミラー方式については、その後ニコンなどとの間で特許争いがあったが、日本の共通技術となり、日本のカメラ業界を世界一に押し上げていった。 このアサヒレフレックスは、上記の「ニューカメラ診断室」の第二回目に取り上げられた。このカメラについていたタクマー・レンズの解像度の測定結果に納得がいかないと、松本社長は、担当ドクターの大学の研究室に怒鳴り込んだ。それほど、この製品にかける気迫があったのである。 ひとつ紹介したが、こんな話が「国産カメラ開発物語」に35編、「戦争とカメラ」に32編載っている。それぞれが実に面白い。技術開発がロマンであること、開発の苦労とそれを達成したときの喜びがどんなであるかを、同じ理系・技術系人間として想像できる。著者の小倉さんは、巧みな文筆家である。技術系の人間はどちらかというと、味も素っ気もない文章しか書けないものだが、この人は、非常に簡潔に、本質をつき、しかも読ませるいい文章を書いている。感心したことのひとつである。 「物語」にも「戦争と」にも取り上げられている、カメラと兵器技術との関連は、私としては初めて聞く話だった。ニコンは海軍お抱えの光学兵器製作工場だった。軍艦の撃つ大砲の着弾を計測し、射角を調整する装置は、カメラのレンジファインダーにつながった。爆撃機の爆弾投下の照準器が現在のカメラに欠かせないオートフォーカス(AF)機構の先駆となった。終戦後、それまで兵器オンリーの会社だったニコン(当時は日本光学)がカメラなどのメーカーに転身できた技術力は、兵器産業によって培われたのである。 最後にもう一度、病気の話に戻ると、日本のカメラ業界を、かくも発展させたひとつの要因は、日本人の、特に男性の「病気」のせいである。私が観察するところ、不思議なことに、アメリカやヨーロッパでは、この種の病気にかかる人は、非常に少ない。彼らは、写真は写ればいい、という合理的精神の持ち主で(別の意味ではケチである)、大枚をはたき、使いこなせもしない高機能を持った機材を購入するような愚をしない。必要にして十分な機材で満足するのである。ところが日本人男性は、いったん踏み込むと、とことんのめり込む。プロしか要らないような最高性能の機材を求めたがる。この病気にかかる人が、かくも多いことが、日本のカメラ業界の底上げに大いに貢献したのである。病気もまあ、悪くないということか。 |